| ��18�b |
�u���ʎq�����v����u�d���q�����v�ւ̈ڍs
2016�N6��20���@�F�����@��
�u�t���[�S�Ȏ��T�E�B�L�y�f�B�A�v�����܂��ƁA
�A�C���V���^�C�����\�z�������ΐ����_�ɂ��āu�l�ނɑ傫�ȗ��v�������炷�l�Ȍ����ƌ�����̂��ƌ����^��v�Ƃ̐��A�c�c
�����āA���̌��ʂɗ��������܂��B
���ʎq�����Ɋ�Â����d���ʂ̗��_�I�𖾂ɂ����1921�N�̃m�[�x�������w�܂���܂����B
�悸�́A���́u���̗��q���i���ʎq�j�v�Ɋւ��āA�S�Ȏ��T�i�f�W�^���������}�Ёj���Q�Ƃ��A���̂悤�ɉӏ����������Ē����܂��B
| 1 | ���̃G�l���M�[�� h�� �Ƃ����ЂƂ����܂�̑傫���ł���肳��� | |
| 2 | �Œ�� h�� �̃G�l���M�[�������̏�Ԃ͌��q(�܂��͌��ʎq�Ƃ����C���q�Ƃ��Č������̂���)��1������ | |
| 3 | �P�ʑ̐ϒ��Ɍ��q�� n ����Ƃ���ƁC�ÓT�d���C�w�̌��̃G�l���M�[�Ƃ̊W���C
�i�A���Ah�̓v�����N�̒萔�j |
|
| 4 | E0�i���̓d��̐U���j���傫���Ȃ�ƌ��q�̌��͑����邪�A �X�̌��q�̃G�l���M�[ h�� ���ς��킯�ł͂Ȃ��B |
�@
�@���������ł���ˁA
���́A���́u���ʎq�����v��ے肵�悤�Ƃ��Ă���̂ł��B
�@�d���g���d�����^�ԁi�K�C�h����j�Ƃ���ƁA�d���g�����̈��ł��B
�Ƃ��낪�A�O�b�u��17�b�@�\����ʂƂ���������ꂽ�d�C��R�v�ɉ�����u���茋�ʁF2�v�����܂��ƁA1MHz�i���M���ԁF1㍃�b�j�̌𗬂�1�p���X���A�d���i�����P�[�u���j��600�b�ڍs����ƁA���̌�1�p���X�̔��M���Ԃ��A�ق�1.5�{��1.5㍃�b�Ɉ����L����Ă��邱�Ƃ�������܂��B
�ƂȂ�܂��ƁA�M�����i���j�́A1/1.5�{�ɕω����Ă��܂��܂��B
����ł́A��Ɍf�����u��1���v�́g���̃G�l���M�[�� h�� �Ƃ����ЂƂ����܂�̑傫���ł���肳����h�����Ă��܂��܂��B
�@�������A��ʓI�ɂ́A���̗l�Ȃւ��Ȃ���ƈقȂ��āA�𗬂Ƃ����ǂ��A���g�ł̊ώ@���s���܂�����A���̂悤�Ȏ����ɋC���t�����Ƃ͂���܂���B
������A�A���g�Ŋϑ�����A�u��17�b�v�́u���茋�ʁF3�v�̂悤�ɁA1MHz�̌𗬂́A600�b��ł��A1MHz�̌𗬂Ƃ��Ċϑ�����Ă��܂��̂ł�����I
�ł��A1�p���X�A�����A���ʎq�́A1MHz�̌��ʎq����A��0.67MHz�̌��ʎq�֕ω������ƍl������Ȃ��Ȃ�܂��B
����͕ςł��B
�@����ł��A���������̃~�X�ł͂Ȃ����Ǝv������������܂��傤���A���́u���茋�ʁF1�v���������������B
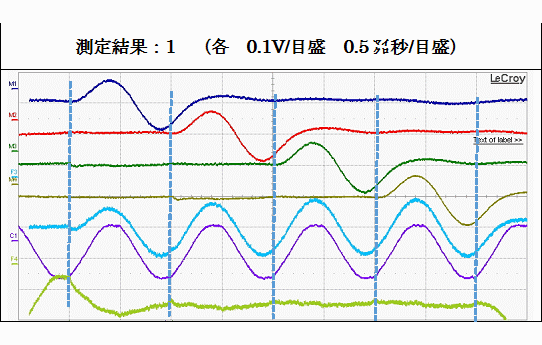 |
���̑��茋�ʂ̂悤�ɁA�F�A�ԐF�A�ΐF�A�J�[�L�F�̊e�X�A�T�C���g�i1MHz�F������1㍃�b�j1�p���X�����A1�������i1㍃�b�j�����Ԃ����炵�āi���������A���p���X�̏ꍇ�̂悤�Ɂj���肵�A������e�g�����Z����ƁA��F�́i�[���I�j�A���g�܂��B
���̍��Z�����A���g���A�ʏ�̘A���g�ł̑���l�ƈ�v���邱�Ƃ��A���ΐF�́i���Z�l�|�A���g�j�����Z�l���A�[���{���g���������Ƃ��疾�炩�ƂȂ�܂��B
�@�����Ɖ��ȗ���f���܂��傤�B
�d���i�p���X�W�F�l���[�^�j����A20MHz�̋�`�g�M�����A�d���o�͕��ƁA�O�b���l��600�b���̓����P�[�u���i���[��50���̒�R�Ő����I�[�����j���[�ւ̏o�͂��A���ʂƂ��āu���茋�ʁF2�v�܂����B
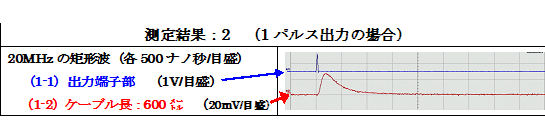 |
�i���F�d���̃s�[�N�l���A���͎���1V����A600�b��ł�20��mV�ւƌ������Ă���̂ŁA��̑��茋�ʂ́i1-2�j�́A�d���̖ڐ����A���͔g��50�{�ŕ\�����Ă��܂��j
�@���̂��̂悤�ɕω����Ă��܂��̂ł��傤���H
��ʓI�ɂ́A600�b�̓d���̒�R�ɂ�鑹���̌��ʁi�O�b�̌v���ł́A��R�l�́A77.4���j�ŁA�v�Z����ƁA��0.56V�ƂȂ锤�ł�
�i���́A�u�}�F1��2�v�Q�Ɓj
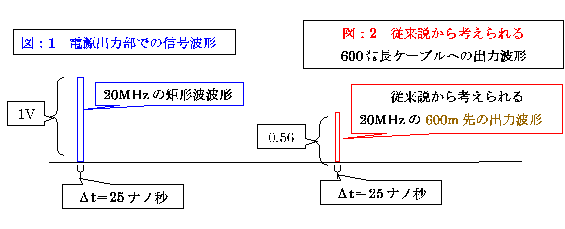 |
�@���̂悤�Ɂu�}�F1�v����A�u�}�F2�v�ɕω����U��Ȃ�A�u���ʎq�����v�̌��ʎq�̐U�����͈��i20MHz�j�̂܂܂ŁA����n���d���̓��̒�R�N���Ō��������ƍl�����܂��傤���A�������ʂ́A�u���茋�ʁF1-2�v�̂悤�ɁA��`�g�i20MHz��`�g��1�p���X�̔��M���ԁF0.025㍃�b�j����S���ό`���A���M���Ԃ���G�c�Ɍ��āA2㍃�b�ƁA��100�{�ɑ��債�Ă���܂��B
�i���̌����A��ɏЉ�܂����A�A���g�ɂ��ώ@�ł́A�O�b�Ŕے肵���u�\���R�v�Ƃ��ĕЂÂ����āA�����̕��͂��ڂɂ������Ƃ��Ȃ��g�`�ł��傤�j
�@���̂悤�ȕό`����d���g�𗱎q�I�ɕ\������ɂ́A���q�P�ʂ�U�����Ƃ��Ă͕s�K�ŁA���ׂ����P�ʂŁA���q��\�����ׂ��ł��傤�B
���ׂ̈ɂ́A�u�}�F3�v�̂悤�ɁA��`�g�M�������ԓI�ɍו����邾���łȂ��A���x�I�i�d���I�j�ɂ��ו��������u�ʎq�I�d�C�M���v�̊T�O�̓������K�v�ƂȂ�܂��傤�B
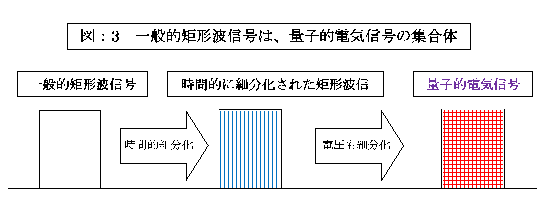 |
�]���āA�u���茋�ʁF1�v�̊e�ώ@�g�`�́A�T���I�ɁA�ʎq�I�d�C�M���i���ԓI�ɂ̓v�����N���ԁitp=5.391 06�c�c �~ 10-44 s�j�ŕ������ꂽ�M���j�u�}�F3�v���g�̈�����ۈ�i���j�Ƃ��ĕ\�������́u�}�F4&5�v�̂悤�ɁA������������ł��傤�B
�i���̂悤�ȁu�ʎq�I�d�C�M���v���^�ԁu�d���g�v��{���ł́A���́i�d���g�́j���g���ɑS�����W�ȑ��݂Ƃ��āA�����āu���q�v�Ƃ͕ʂ̖��́u�d���q�v�Ɩ������܂����j
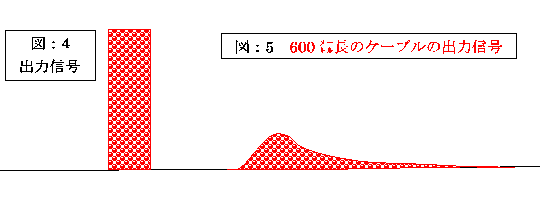 |
�@���̂悤�ȁu�d���q�v���l�����܂��ƁA�u�����v�Ƃ́A����Ȃ��������ꋭ���́u�d���q�v�Ƃ�������f�������邱�Ƃł���A�𗬂Ƃ́A���B��ʓI�Ȍċz�̂悤�ɁA��胊�Y���ŁA�u�d���q�v�Ƃ��������A�f������z�����肵�Ă����ԂƗႦ�邱�Ƃ��o���܂��傤�B
�@�����āA���g���Ƃ́A���̑��̃��Y���i�z������f������̊Ԋu�j�ƂȂ�܂��傤�B
�ܘ_�A��ʓI�ȓd���g�ɑ��Ă��A���́u�d���q�v�Ƃ��������A�f������z�����肵�Ă������ƗႦ�邱�Ƃ��o���܂��傤�B
�����āA�]���̂悤�ɓd���g�̐U�������A��Ƃ��A���Ƃ��̐U�����ɗႦ�邱�Ƃɂ���āA�����̌�����U������Ă����̂��Ƒ����܂��B
�i�⑫�j
�@����́u���茋�ʁF1�v�̂悤�ɁA1�g���i1�p���X�j�̃T�C���g�ł̑��茋�ʂł́A�T�C���g����̈�E���F�߂���̂ɁA�����𐔔g���Z������A�A���g�ő��肷��ƁA���̃T�C���g��ԂŊϑ�������́A�V�w�R�����u�X�̓d���C�w�@��6���@�𗬗��_�͍���̘O�t�x��23�łɌ��邱�Ƃ��o���܂��̂ŁA���̕����������ɔ����f�ڂ��܂��B
���A���̑���́A�R�C���ƃR���f���T��ڑ������u���U��H�v�̎����ł̑��茋�ʂł��B
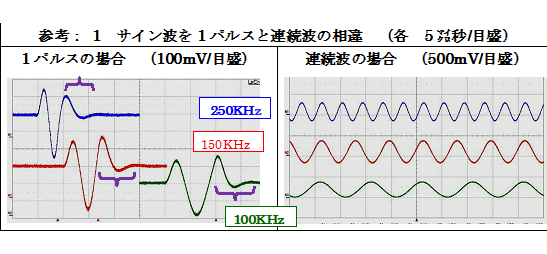 |
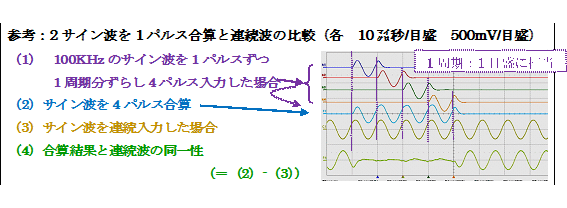
|
�@�O�́w��17�b�@�\����ʂƂ���������ꂽ�d�C��R�x�ɉ�����A�u���茋�ʁF2�v��1�g�����ł̃T�C���g����̈�E�́A�w��14�b�@�g�����X�̗��_������ł��i�𗬕ҁj�x�́u���茋�ʁF1�v�ɂ����邱�Ƃ��o���܂��B
�@���̑���ł��A���̂悤�Ȍ��ۂ͗e�ՂɊϑ��ł��܂��̂ŁA�u���ʎq�����v�͂��ޏꂢ�������ׂ��Ƒ����܂��B