『コロンブスの電磁気学』の要旨(18) 直流送電の交流送電に対する優位性
2011年6月11日
宇佐美 保
超伝導材料以外の一般的導体(例えば、銅線、アルミ線など)には、固有の抵抗値が存在します。
その抵抗値がRオームである電線に、Iアンペア電流をその末端まで流すと、その間に低下する電圧をVボルトとしますと、オームの法則から、次のような関係が得られます。
V=I×R
この関係は、直流であろうと、交流であろうと同様に成立します。
この面では、直流の交流に対する利点が存在しません。
では何故、長距離送電に於ける、直流の交流に対する優位性が存在するのでしょうか?
高周波信号の伝送に関しては、「表皮効果」と言う現象によって、伝送量の減少が発生すると言われています。
この表皮効果を検討する為、高周波信号の伝送の実験をしてみると、確かに、伝送する信号が高周波になるほど、その伝送量の減少が確認されます。
例えば、次の「図:1」のように、サイン波発生器から、各種周波数(1〜4GHz)のサイン波(1V=500mV/-500mV)を同軸ケーブル(1メートル長)へ出力し、同軸ケーブルで伝送されるその信号波形をオシロスコープで観測して「測定結果:1」を得ました。
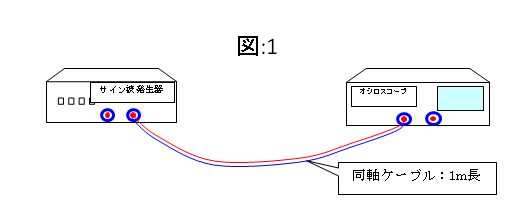 |
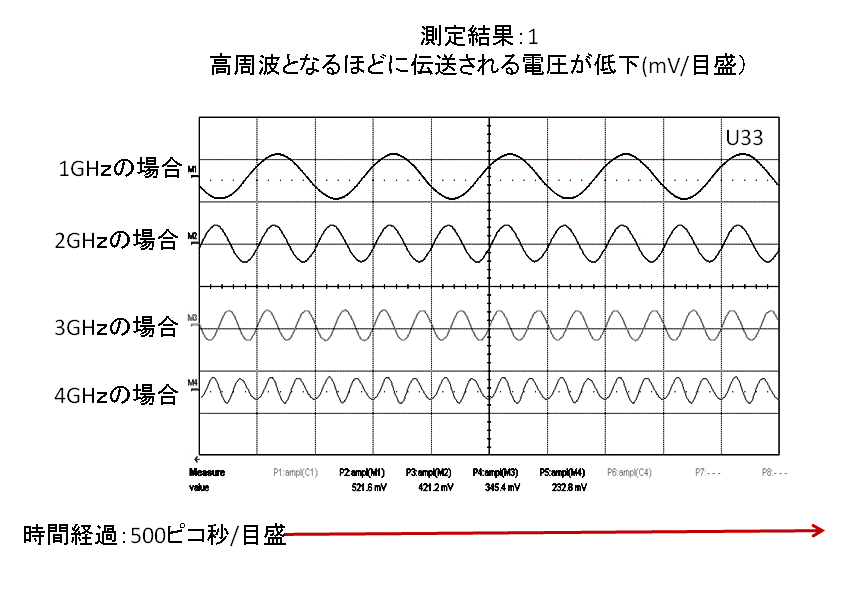 |
しかし、このような現象は、何も高周波信号のみに発生するのではないのです。
例えば、ファンクションジェネレーターから、1MHzのサイン波(出力電圧:1V)を1メートル長の同軸ケーブルに出力して、その伝送波形を末端部(50Ωで終端)で差動プローブを用いて測定しました。
その後は、この先に、100メートル長の同軸ケーブル、更に、その先に100、200、400メートル長の同軸ケーブルをつなげて、1メートル長の場合同様に、伝送されてくる電気信号の波形を観測しました。
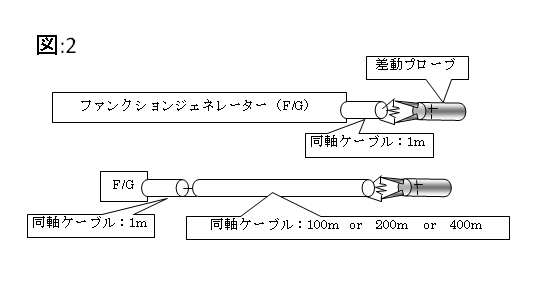 |
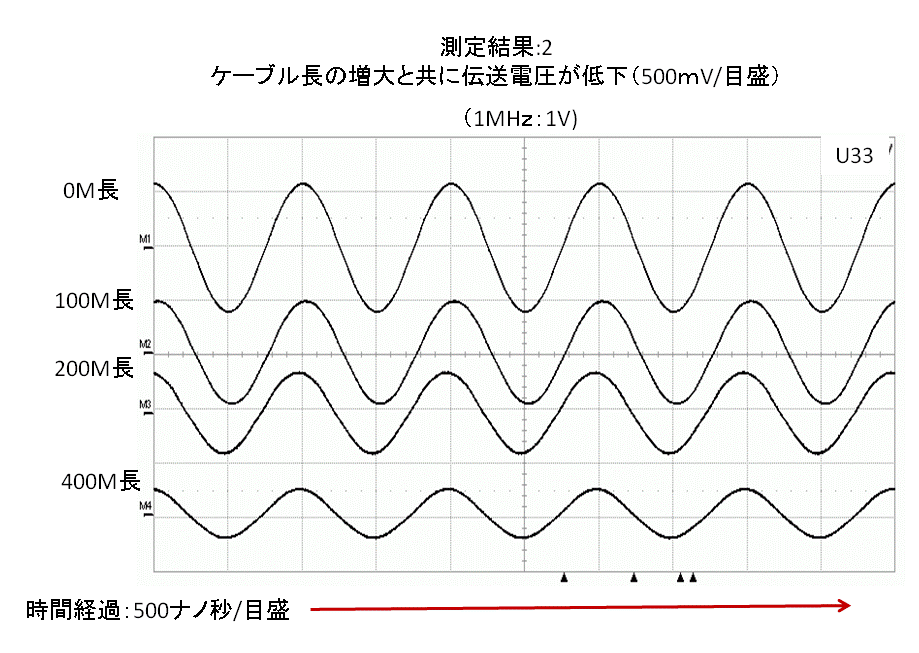 |
(注)ケーブル長:実質的ケーブル長は、この1m分が常に加算されて、0mの表記では、1m、100mと表記してある場合は、101m、200mの場合は201m、400mとの表記では401mとなっています。
この結果に見ますように、伝送信号の周波数がGHz帯まで高くなく、1MHzでも、伝送路長が100メートル……と長くなれば、信号の劣化(ピーク/ピーク値の減少)が認められます。
次には「測定結果:3」に、1MHzの1パルスのサイン波(出力電圧:1V)が、1メートル長の同軸ケーブル、更に、その先に、100メートル長の同軸ケーブル、200メートル長の同軸ケーブル、更には、400メートル長の同軸ケーブルを伝送された場合の信号の劣化状態を掲げました。
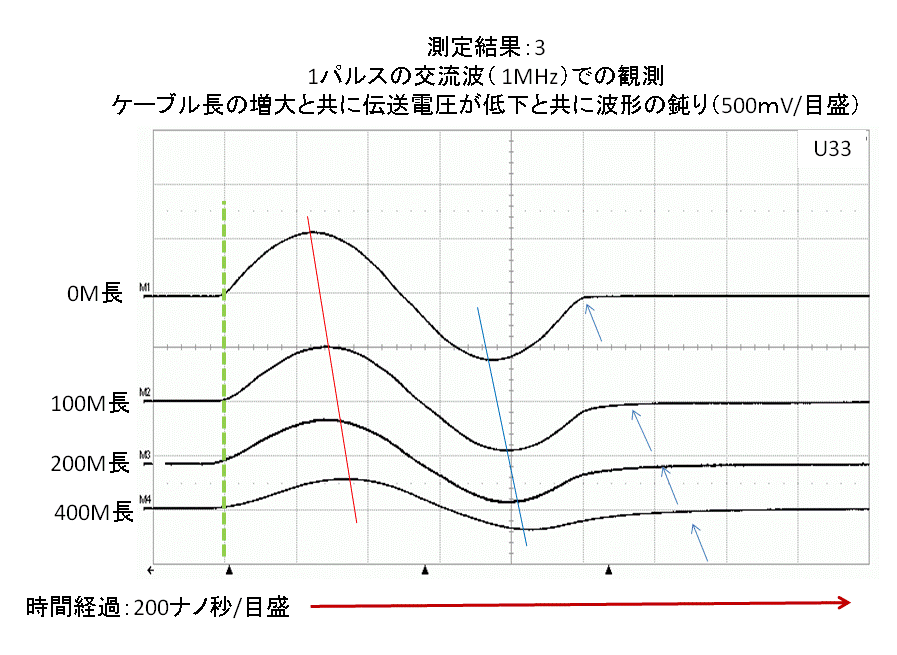 |
確かに、1パルスのサイン波信号の場合も、先の連続信号の場合同様に、出力波形は小さくなっています。
しかし、よく見ますと、そのサイン波の形状が変化しています。
即ち、そのピークの位置が後退しているのです。
この伝送波形の変化の様相をより明確に認識する為に、次はサイン波に変えてクロック信号により、上記と全く同様な測定を行い「測定結果:4」を得ることが出来ます。
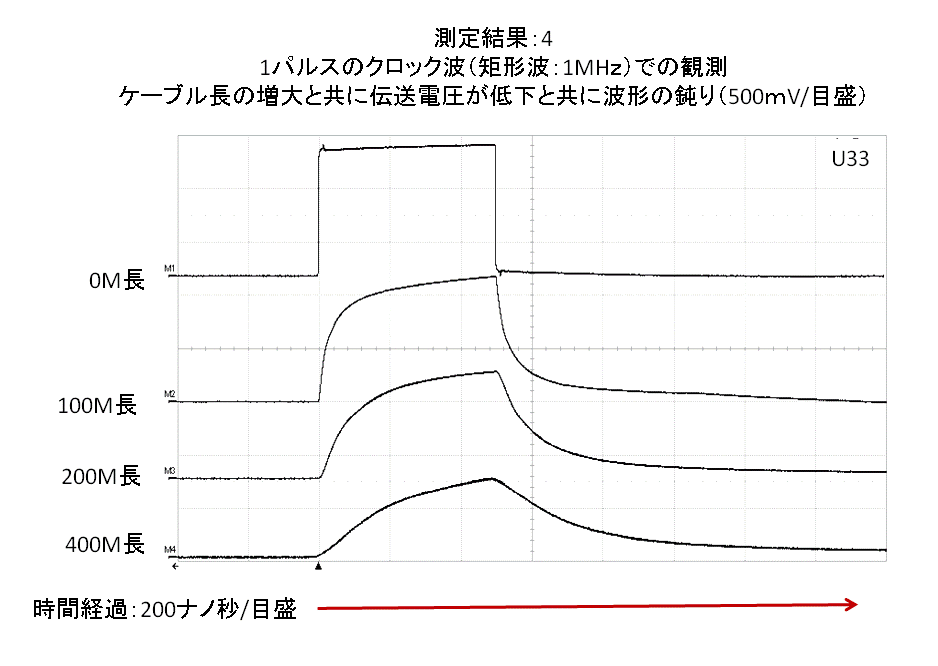 |
この結果から、クロック信号の場合は伝送波形の変形が、サイン波の場合以上に、よりはっきりと認識できます。
即ち、直線的であった立ち上がり、立下り部の形状が、同軸ケーブル長の増大と共に、なだらかな曲線へと変化しています。
そして、ケーブル長の増大と共に、この変形の度合いが増加し、クロック信号の保持電圧(今回の場合は、1ボルト)に達することなく、立下りを余儀なくされている状態が観測されています。
では何故、このように伝送されるクロック信号(サイン波信号)の立ち上がり/立下り特性が劣化するのでしょうか?
このような現象は、従来の「表皮効果論」では説明できません。
更には、この従来の「表皮効果論」では説明できない現象を次に示します。
例えば、同軸ケーブル長を100メートルとし、出力信号に定常状態が認められるように、前項同様に1MHz(1ボルト)の1パルスのクロック信号を入力した「測定結果:5」が次のようになるのです。
(ケーブルの末端は、50Ωの抵抗で終端処理)
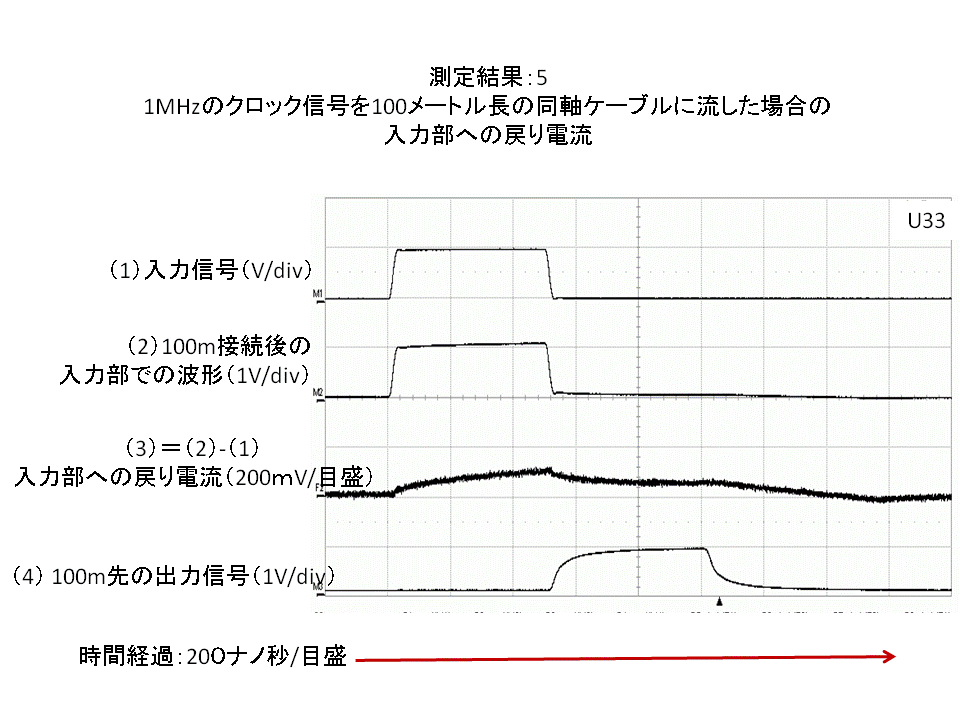 |
いかがでしょうか?
入力側への戻り電流が観測されているのです。
このように、入力側への反射現象の存在を、従来の「表皮効果論」で説明するのは不可能です。
そして、その戻り電流が末端からの反射ではないことが、末端での出力電圧よりも先に測定されているのですから、ケーブル起因の反射であることが明らかです。
この反射現象の原因として考えられるのは、電線(伝送線路を構成する導体)の抵抗の存在です。
伝送線路中に抵抗が存在すると、そこを流れる電流に反射現象が発生します。
その反射は、ケーブルの末端へ向かう際にも、反射されて入力側に戻る際にも発生します。
即ち、何度も何度も反射を繰り返しながら(多重反射されながら)電気信号は末端へと進み、又、一部は入力側へも戻って行くのです。
(この件の数式的説明は、次の「『コロンブスの電磁気学』の要旨(19) 伝送線路の多重反射現象」に譲らせて頂きます)
この現象を見る為に、先ず、同軸ケーブル(各50cm長)の前後の接続箇所に同一抵抗値の抵抗(カーボン抵抗)を合計5か所設置しました。
即ち、各抵抗間を、(全て同じ長さの50cm長の)同軸ケーブルで結びました。
但し、抵抗値は、12Ω、24Ω、48Ωの3種類としました。
そして、この2メートル長のケーブルの前後に1メートルの同軸ケーブルを接続し、一方の末端をパルスジェネレータに、ケーブルの他方の末端に50Ωの抵抗を設置してそこでの電圧変化を測定しました。
尚、パルスジェネレータからは、100MHzのクロック信号(500mV)を1パルス流し、末端での出力波形を差動プローブで測定し、次の「測定結果:6」を得ました。
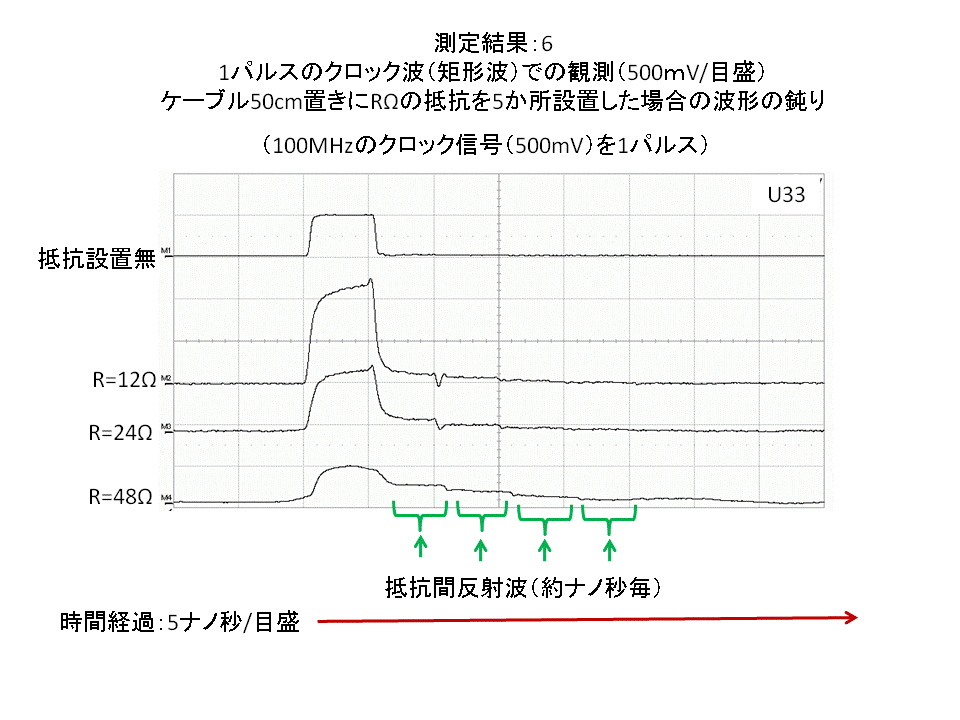 |
この測定結果を見て分かりますように、抵抗の存在により(出力電圧の低下は尤もですが)クロック信号の立ち上がり/立下りは、その抵抗値の増大と共に鈍りが目立ってきます。
特に、48Ωを設置した場合には、立下り部が長く尾を引いています。
そして、この尾の引き具合は、約5ナノ秒(50cm×2/20cm/ns)ごとに存在し、その原因が抵抗間(50cm)反射の結果である事が分かります。
従って、伝送線路中に存在する抵抗に起因する反射現象を繰り返し進行する為に、電送信号の立ち上がり/立下り特性が劣化すすことが判明しました。
次は、「図:3」のように、パルスジェネレータの出力端子に直接10メートル長の同軸ケーブルを接続して(このケーブルの目的は測定結果の考察時点で明らかになります)、それに、抵抗群を設置したケーブルを接続して、パルスジェネレータの出力部、抵抗を数珠つなぎにしたケーブルの先に、更に、1メートル長の同軸ケーブルを接続し、その末端(50Ωで終端処理)での電圧変化を差動プローブにて測定しました。
パルスジェネレータの出力は、10MHzの1パルスのクロック信号(1V)としました。
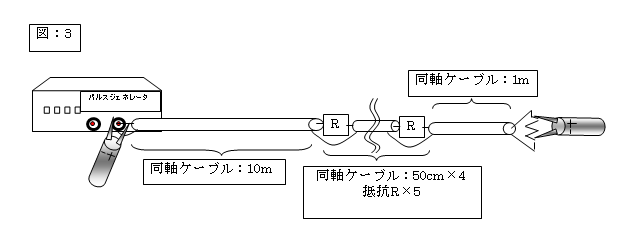 |
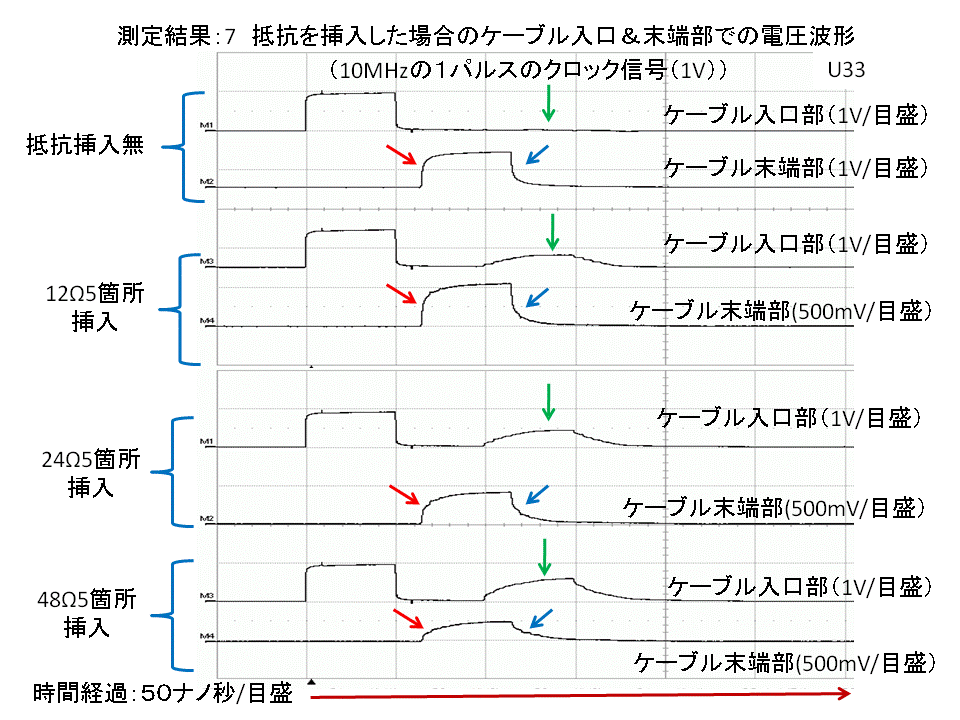 |
この実験結果を見ると、「測定結果:6」の場合同様に、同軸ケーブル間に抵抗が存在すると(即ち、伝送路の導体の抵抗によって)、伝送信号の立上り立下り特性が劣化することが明らかに確認できます。(赤矢印、青矢印部)
更に、パルスジェネレータ出力部では、ケーブルへの入力後約1ナノ秒に、10メートル長の同軸ケーブルの先に設置した抵抗を主因とする多重反射による戻り電流(緑矢印部)も観測されています。
この反射が最終的末端(そこまでの距離は、13メートル(=10m+0.5m×4+1m)からの反射ではなく、最初の抵抗設置位置(10m地点)から開始している事が分かります。
∵ 10mの同軸ケーブルを往復する時間は、約1ns(=10m×2/20cm/ns)
13mの同軸ケーブルを往復する時間は、約1.3ns(=13m×2/20cm/ns)
(勿論、抵抗が挿入されていない場合には戻り電流は観測されていません)
ここまでで検討してきた抵抗は、導体抵抗の如くに均一的に分散して存在せず、50cm置きに存在しています。
そこで次は、この導体自体の抵抗値が異なる、本実験では、本著の中で何度も活躍している銅の丸棒(5φ×1m長)の伝送路並びに、銅の丸棒に変えて、同じ長さのステンレス(銅より電気抵抗大)の丸棒(5φと3φの2種類)で伝送路を組み、100MHz(500mV)のクロック信号(1パルス)を通し、これらの伝送路の伝送特性を比較しました。
尚、極端に抵抗が大きな導体として、厚さ:0.5μmのニッケルめっきを表面に施したガラスの2本の丸棒(径:6.2mmφ、長さ:50cm、抵抗値:約85Ω×2=約170Ω)による伝送線路も併せて検討しました。
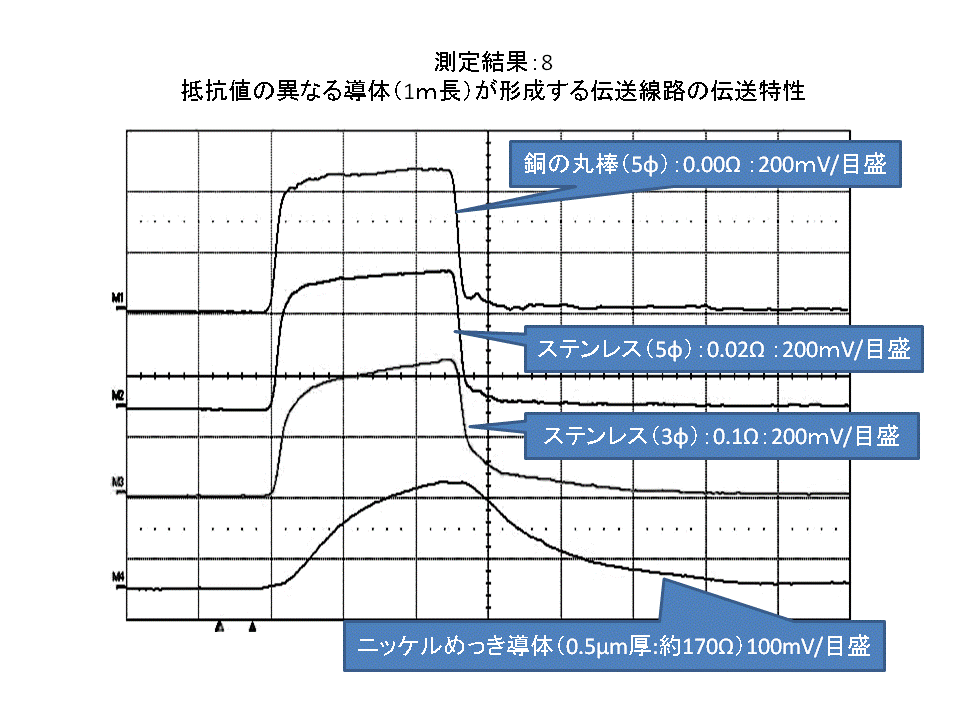 |
この結果に見るように、伝送路を形成する導体の抵抗値が高いほど、その伝送特性が劣化する(信号の立上り/立下り時間が遅くなる)ことがわかります。
従って、抵抗を有する導体が構成する伝送線路を電気信号が多重反射を繰り返しながら進行する為に、立ち上がり/立下り特性が鈍化する事が分かりました。
では何故、連続波入力の場合は、1パルス入力の場合に比較して出力値(ピーク/ピーク値)が大幅に小さくなるのでしょうか?
この件を明確とするために、100m長の同軸ケーブルに100MHz(500mV/0mV)のクロック信号を、連続で入力した場合、又、1パルスのみを入力した場合、2パルスを続けて入力した場合、5パルスを続けて入力した場合、10パルスを続けて入力した場合の観測結果を次に掲げます。
(但し、入力パルスは、この時使用したパルスジェネレータの制約上、各/32BITとなり、33 BIT目に入力された信号も(余計に)観測されています)
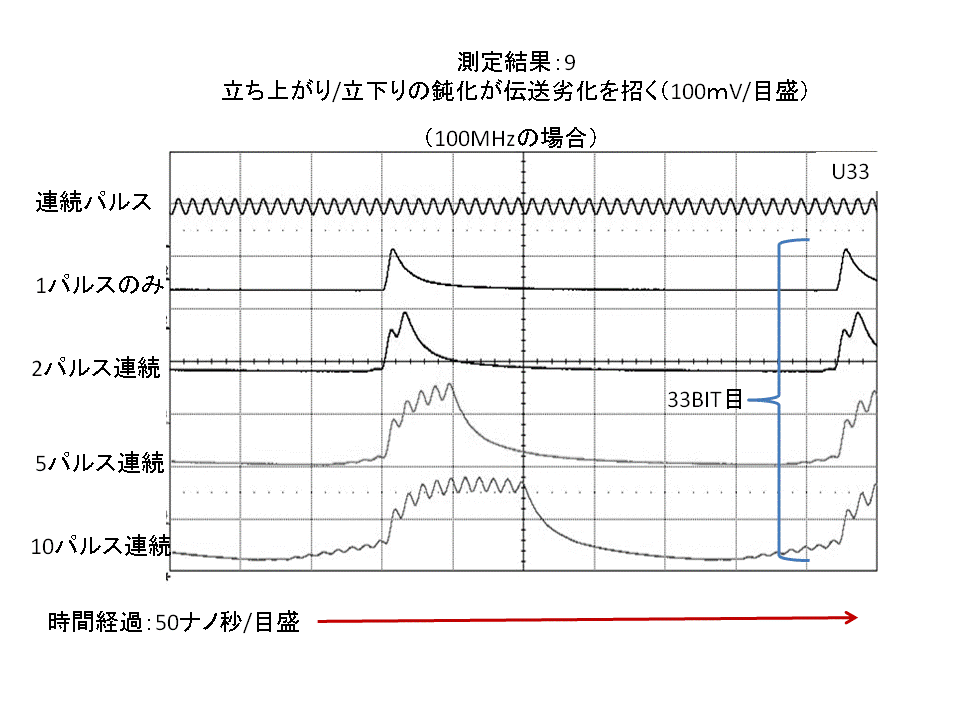 |
この結果を見ますと、1パルスの信号が十分(500mV迄)に立ち上がる前に、立下りを余儀無くされ、その最高値は100mV程度までにしかなれません。
その上に、十分(0mV迄)に立ち下がる前に、次の信号が来てしまうために出力信号の山と谷との高さ(ピーク/ピーク)の差が、極端に小さくなってしまう様子が観測されます。
尚、パルスの数を重ねるに従って(立ち下がり信号の鈍りによる「尾」に相当する部分が重なってゆく為)、出力信号の全体的な高さが、高くなって行く様子も観察できます。
そして、この「測定結果:9」を見れば、直ちに従来の「表皮効果説」の欺瞞に気が付かれることと存じます。
しかし、交流の場合の伝送特性が劣化する原因は、導体中の抵抗に起因する多重反射が原因であることが分かりましたが、これだけでは直流の方が交流より伝送特性が有利である理由がはっきりしません。
そこで、先ず、同軸ケーブル(100m長)からの各周波数(50KHz〜500Mhz)の伝送結果を、出力値(縦軸)のゼロ点を全て同じとして、重ね合わせて表示します。
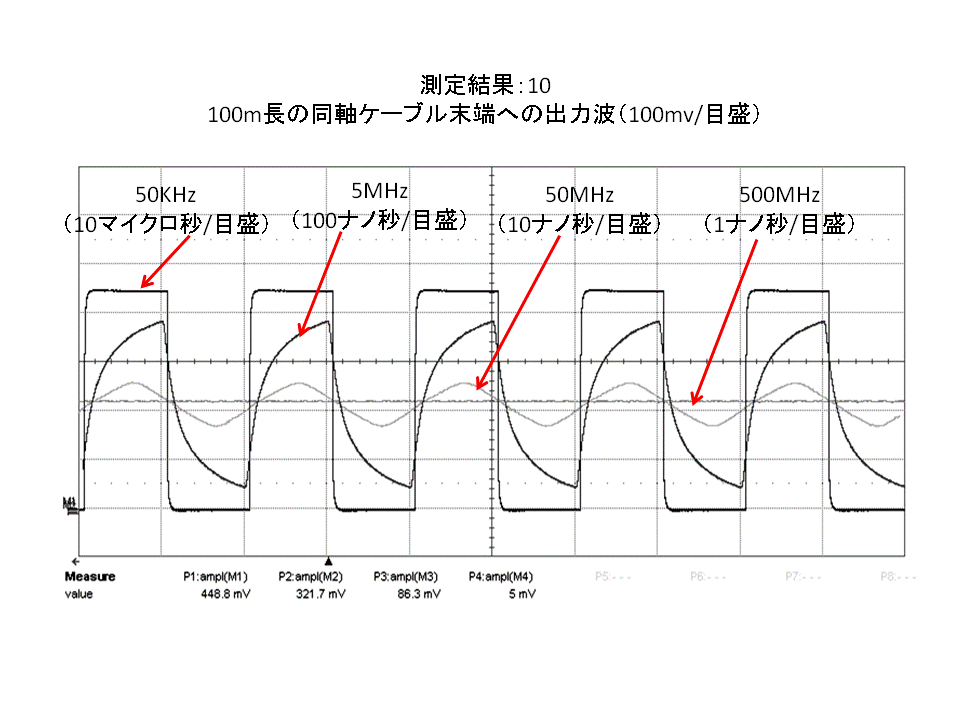 |
この結果を見ると、50Khzの出力結果(ピーク/ピーク値)が約450mv、500MHzでは、約5mVであっても、各周波数の平均出力は、低周波域(50KHzなど)、高周波域(500MHzなど)の両帯域に於いて、入力電圧(0〜500mV)の平均値250mVに近い、約220mVであることがわかります。
即ち、例えどれほどの高周波域となっても、電気量(ここでは、(電圧)×(時間))は低周波域と全く同様に(電気量が劣化することなく)、伝送されているのです。
(即ち、「測定結果:10」の500MHzの場合のように、電圧の山が、平らにならされた感じです。
クロック信号の場合の山が、その高さが1/2となった丘(直流)に姿を変えただけです)
この件を、つぎのような「イメージ図」に纏める事が出来ます。
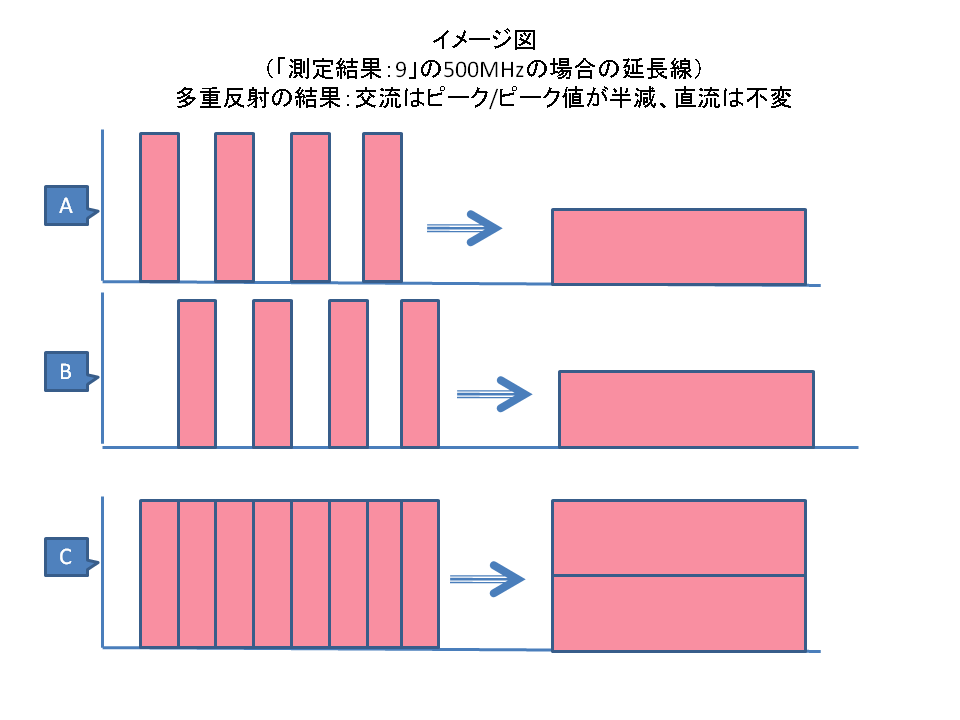 |
このイメージ図の「A」、「B」は、両方ともクロック信号の連続波(交流)です。
そして、先の500MHzの連続波の場合のように、信号の高さが、長い伝送線路を伝送される結果、ほぼ1/2の高さの直流に変化しています。
そして、その「A」、「B」の2者は、反周期ずれて発信されています。
この両者を合体した結果が「C」となります。
この「C」は見方を変えれば「直流」です。
そしてこの「直流」はどんなに長い伝送線路でも、多重反射が原因での減衰がないまま伝送されることが分かります。
明らかに、長距離伝送に於いて、「交流」よりも「直流」が遥かに有利であることが分かります。
「多重反射現象」に関しては、次の「『コロンブスの電磁気学』の要旨(19) 伝送線路の多重反射現象」に譲らせて頂きますが、
詳細は是非とも自著『コロンブスの電磁気学』増補改訂版をご参照ください。
(補足)
電流の反射現象は、伝送線路の特性インピーダンスが変化する箇所で発生しますので、導体抵抗の存在だけでなく、伝送線路の接続部、分岐部などでも発生しますので、「超電導材料」を使用した場合でも「直流送電」が「交流送電」よりも有利なのです。